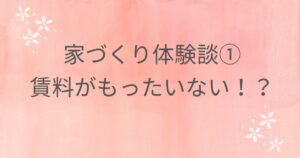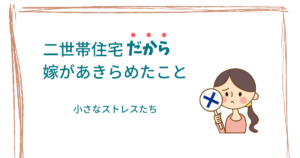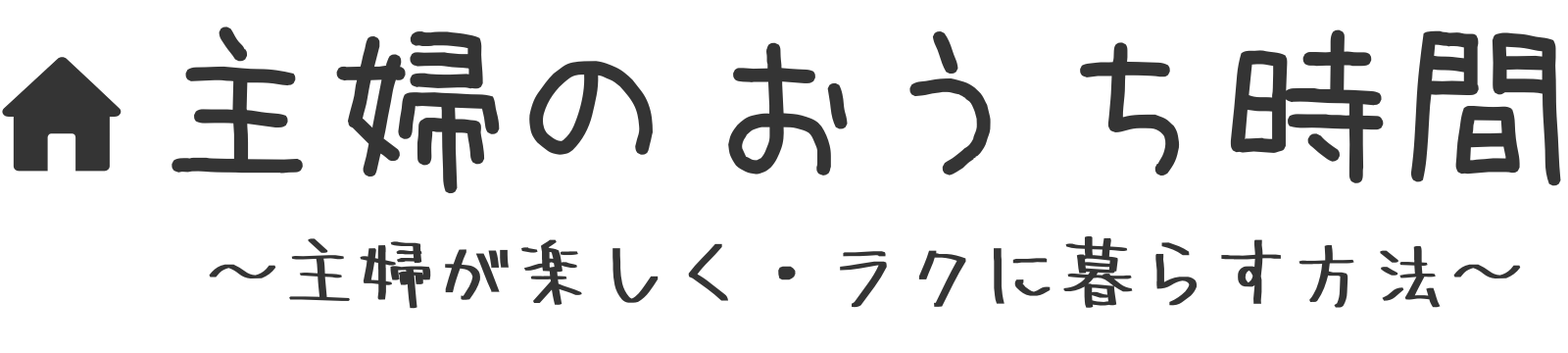二世帯同居を始めるときには、生活費に関するルールをしっかりと決める必要があります。
- 生活費のどれを分けるの?
- 生活費の決め方は?
- もめないルールってあるの?
二世帯同居ならでは問題ですが、身近な人に聞きづらいし、正解がないので悩んでしまいますよね。
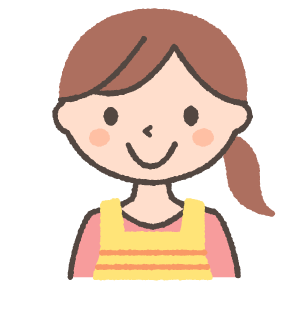
実際に私も、二世帯住宅に住むときに悩みました!
そこで今回は、どうやって二世帯同居の生活費を分けたのか、決め方・ルールの実体験を説明します。
二世帯住宅に関わらず、「同居をする人」「同居を考えている人」はぜひ参考にしてみてください。
二世帯同居の生活費の一覧表
生活費には、
- 「毎月支払いが発生するもの」と「年に1回のもの」
- 「変動する場合」と「固定のもの」
とうように大きくふたつにわけることができます。
その中で、二世帯住宅で折半が必要な生活費は何があるのかを一覧表でご紹介します。
【分けるべき生活費一覧表】
| 食費 | 一緒に食事をする頻度による |
| 生活雑貨 | 洗剤・石鹸・ごみ袋など |
| 光熱費 | メーターが別なら不要 |
| 通信費 | 電話・インターネットの使用頻度 |
| 新聞代 | 誰が読むか? |
| 町内会費 | 町内会費・募金・お祭りのご祝儀など |
| 交際費 | ご近所や親戚づきあい |
| NHK受信料 | 口座振替の場合もあり |
| 修繕費 | 外壁など(頻度は少ないが確実に必要) |
| 外回り(庭)の費用 | ガーデニングや玄関周りなど |
| 住宅ローン | 毎月固定 |
| 固定資産税 | 年一回 |
| 火災保険料 | 年払いは10年払いなど |
このひとつひとつをどう分けるか?をしっかりと話し合っておかないと、トラブルの原因となってしまいます。
一覧表はとても細かく感じるかもしれません。でも、分け方をしっかり決めておくことが二世帯住宅の不満が減ることになるので、漏れることなく話し合いをしましょう。
考慮しておきたいこと
生活費の何をどの比率で分けるかに正解はありません。
二世帯住宅の数だけ、生活費の折半方法があるから難しいんですよね。そこで、生活費を分けるときに考慮すべき5つの判断材料をご紹介します。
頭金の出資状況
頭金をどれだけ出したかはとても大切です。
特に住宅ローンと頭金の比率は大きく関係するものです。
「親世帯が頭金を多く出したから、住宅ローンは子世帯が多く負担する。」
などと、お互いが納得する分け方が理想です。
※【家づくりブログ⑨】二世帯住宅の頭金でわが家の実例を詳しく説明しています。
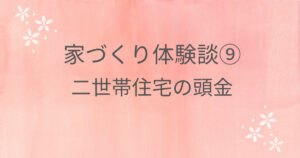
住宅ローンの負担額
最初だけ出費が必要な「頭金」とは違い、「住宅ローン」は毎月大きな出費ですよね。
そんな住宅ローンの額は、生活費の分け方に大きく反映させるべき項目です。
「住宅ローンは子世帯がすべて持つから、光熱費は全て親世帯がもつ」
なんていう話も聞きます。
ただ個人的には、光熱費を全て親世帯が払うと、日々の水道などの使い方を監視されているようであんまり好きじゃないかなぁと思っています。なので、わが家は光熱費は対等に人数で割っているため、親世帯に気をつかうことはしていません。
就労状況
親世帯がバリバリの現役で働いているか、すでに退職して老後を送っているかといった、親の就労状況が大きく影響してきます。
逆に、子世帯でも子育て中で奥さんが仕事をセーブしている場合もありますしね。
就労状況は日々変わっていくものなので、親世帯が現役引退するまでは多く払ってもらうなど、臨機応変に対応するとよいでしょう。
家族の人数
単純に家族の人数で生活費を分けるのが一番楽だなぁと私は思っています。
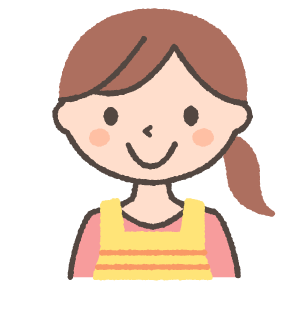
我が家は、親世帯2人、子世帯4人なので、1/3と2/3で分けています。
使用頻度
新聞やWi-Fiなどは、使用頻度で決めるのも良いでしょう。
実際、我が家は新聞はほぼ親世帯しか読まないので、子世帯は一切負担していません。
二世帯同居のルール決めはいつする?
生活費はルールを決めることが大切です。では、ルール決めはどのタイミングですべきかを紹介します。します。
初年度に決める
生活費の分ける方法は一番初めが肝心です!
まずは生活費にどんなものあるのか、先ほどの生活費一覧表を参考に書きだしてみましょう。そのうえで、先ほどお伝えした考慮すべきことを参考に、あなたの家にあった分け方を決めるといいですね。
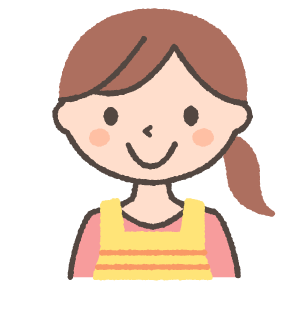
最初が肝心です!初年度を適当にすることは避けましょう!
年払いを含めて、最初の1年で生活費を確定できます。
臨機応変に対応する
初年度にルールを確定させることが大切ですが、その後の変化に対応することも大切です。
- 実際に生活を始めたら分け方がおかしいと感じた時
- 最初のルール決めで忘れていた項目を発見した時
- 家族の就職状況・体調など変化があった時
こんなときは、すぐにまたルールを決め直しましょう。
双方が納得するやり方を探すのが、二世帯住宅が上手くいくコツです。義両親とお金の話をするのは気持ちのいいものではありませんが、変更が必要と感じた時は柔軟に対応することが大切です。
親が退職した時を考える
二世帯住宅を建てた時、親世代が働いていて収入があると、親世帯が生活費を多く払うパターンがあります。そこで忘れてはいけないのが、親が退職する時期は必ずやってくるということです。
思っている以上にあっという間に親の退職はやってくるものです!
その時には、今後の生活費の分け方をしっかりと話し合うことを忘れてはいけません。子世帯は、「いつか親世帯は収入が少なくなる」という意識を持ち続けることが大切です。
お互い言い出しづらいですが、退職前に話し合いをしてみましょう。
誰が話し合う?
話し合うメンバーというのはとても大切です。ただ、円滑に進むメンバーは誰なのか?は、その家庭によって違うので正解がないのがむずかしいところ。
間違ったメンバーで話し合うと、トラブルになることもあるので注意しましょう!
では、話し合うパターンをふたつ紹介します。
大人全員で話し合う
一緒に住む大人全員で話し合うことが一番トラブルのリスクが少ない方法です。
話し合いに参加しない人がいると、あとで異議を申し立ててくる・・・
なんてこともありますからね。
一緒に住むということは、小さな不満が大きな不満に変わっていきやすいんですよね。
だからこそ、全員でお金の話は話し合うのがベストです。
代表者が話し合う
先ほど二世帯住宅のお金の話し合いは、家族みんなでとお伝えしました。
とはいえ、必ずしも全員がいいとは限らないパターンがあるのも事実。
- 家計にノータッチの人
- なんでも難癖をつけるタイプの人
こんなタイプの家族が参加することで話が進まない場合もあるわけです。夫婦の中で誰が適しているかを考えて、出席する人を決めることも大切です。
そして夫婦のどちらかのみ参加する場合は、事前に夫婦でのこまかい部分まで話し合うことを忘れずにしましょう。
わが家の場合
我が家の話し合いメンバー
- 親世帯 → 義母のみ(義父は家計にノータッチ)
- 子世帯 → 夫のみ(嫁は言いづらいため)
こんな感じに、夫が話が通じて臨機応変に対応でいるタイプだったので、嫁である私はあえて表舞台には建ちませんでした。ここらへんは、ほんとそれぞれのタイプによって変わるもの。ただし、全員参加しない場合は事前に夫婦でしっかり相談が大切です。
もめなベストメンバーで話せるのが理想です!
実例紹介
では最後に、実際に二世住宅で同居をしているわが家の実例を紹介します。
| 項目 | 親世帯 | 子世帯 |
|---|---|---|
| 食費 | それぞれで負担 | それぞれで負担 |
| 生活雑貨 | × | × |
| 光熱費 | 1/3 | 2/3 |
| 通信費 | 〇 | × |
| 新聞代 | 〇 | × |
| 町内会費 | 〇 | × |
| 交際費 | 〇 | × |
| NHK受信料 | 〇 | × |
| 修繕費 | まだ発生していない | まだ発生していない |
| 外回り(庭)の費用 | 〇 | × |
| 住宅ローン | × | 〇 |
| 固定資産税 | 1/2 | 1/2 |
| 火災保険料 | × | 〇 |
こんな感じに分けています。特徴としては、
- 光熱費は人数比(親世帯2人:子世帯4人)
- 固定資産税は毎年完全に折半
- 住宅ローン・火災保険といった大きな出費は子世帯
- その他小さな出費は全て親世帯
といったところです。
表の○×でこそ親世帯の〇が多いですが、金額で言ったら子世帯の方が多いことになります。そのかわり、細かい出費や、町内会の仕事は全て親負担。我が家の場合は、親が70代と高齢なので子世帯の割合が多くても納得しています。
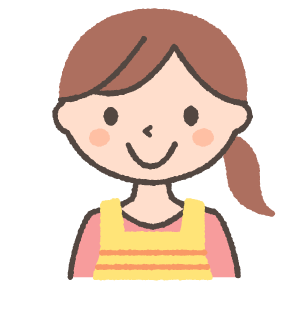
なにより、子育ての手助けやおすそわけを沢山いただいているので、生活費とは別のところで助けられています!
みんなが納得する分け方を目指そう
ここまで、二世帯住宅の生活費の分け方を紹介してきました。
正解がないのが一番難しいとろこですが、義両親ともめるのは絶対に避けたいし、みんなが納得のいくお金の分け方をしたいものですよね。
二世帯住宅で義両親と快適に過ごすためには、もめごとはひとつでも減らすことが大切です。ぜひ今回の記事を参考に、家族みんなが納得する生活費の分け方を実現させましょう!