子どもが小学校に入学するときには、楽しみと同時に不安や疑問を感じるものですよね。
私は小学生の子どもがいる母なのですが、やはり子どもの入学前はドキドキしていたものです。しかも、いざ入学してみると、想像もしていなかったことがたくさん!
ということで、今回は実際にわが家でおきたこと、周りのお友達でおきたことを元に、小学校入学に必要な親の心構えについて説明します。
「こんなパターンもあるのかぁ」とぜひ参考にしてみてくださいね。
- 小学校入学が不安な方
- 小学生の親の心構えを知りたい人
- 小学校生活をスムーズに始めたい人
1年生の4月は忙しい!
1年生の4月は環境の変化も大きく、親子そろって忙しい時期です。
- 4/1から学童スタートでお弁当づくり
- 入学式から1週間くらい午前帰りのためのお弁当づくり
- 大量の書類記入
- 保護者会での自己紹介 など
- 4/1から学童スタート
- 親がいない登下校
- 新しいお友だちとの人間関係
- 学校のルールを覚える
- ずっと座って勉強をする
- 一番年上だった園時代とは違い、一番年下という環境
- 男性の先生も多い環境 など
とにかく4月は精神的にも肉体的にも忙しい月になります。
宿題は親のチェックが多い!
小学校に入学すると、毎日宿題が出されます。
しかも、低学年のうちは親が宿題をみることが多くあります。
- 音読を聞いて、プリントにサインをする
- ドリルの丸つけをする
主にこのふたつですね。
でも、必ずこのふたつがあるとは限りません。

わが家の場合、兄は、音読を10回聞く&ドリルの丸つけが毎日あり大変でした。
しかし妹の時は、音読の宿題もなく、ドリルの丸つけも先生がするので家ではノータッチでした。
同じ小学校でも担任の先生によって、宿題の量や親のチェックの多さは全然違うんですよね。



なんて綺麗ごとを言っても、宿題は毎日のことなので、親のチェックが多いと正直地味にキツイです・・・。
毎日時間がないのに、宿題チェックという作業が増えるのはつらいですよね。
書き順まで確認すると安心!
親が宿題のマル付けをする・しないに関係なく気をつけたいのが、「字の書き順が正しいのか?」ということです。
書き終わった文字だけをみても、書き順があっているかは分かりませんよね。
実は兄が1年生の時に、丸つけはしていても書き順までは見ていなくて、ある時書いている姿をみたら、書き順が間違いだらけだったのです!!
一度間違って覚えると、直すは難しいです・・・・。



1年生の時に、しっかり書き順通りに書いているか確認すればよかったなぁと後悔しています。
1年生のうちに「書き順は大切」という考えをを身につけないと、この先ずっと適当に漢字を覚えていきます。(わが子で経験済み)
子どもの宿題をみることで、自分も書き順が間違えていたことに気づくこともありました。
不安な時は、子どもにバレないように「〇〇 書き順」とスマホで検索すると正解が分かります(笑)
年度始めは、ノートの写真を撮ろう!
学校で使うノートは、マス目の大きさに指定がある場合があります。
私の子どもの小学校では、新年度の1冊目は毎年学校から配られますが、そのノートを使い切ったら、同じマス目のノートを家庭で購入するというルールでした。
でも、マス目の大きさなんて覚えていられないですよね。だから年度初めにノートを写真を撮っておくと購入するときに便利なのです。
- 店先でもマス目をすぐ確認できる
- 子どもの突然の「ノートがなくなった!」に即対応できる
- 今年使っているノートの種類(国語・算数など)が分かるので、他の教科のノートの残りは大丈夫か子どもに確認できる
- 写真を夫婦で共有しておくことで、どちらかがすぐ購入できる
年度初めにノートの写真を撮っておくだけで、臨機応変に対応できるんですよね。そして「なんでもっと早く言わなかったの!?」とならないように、購入時は一冊多めに買っておくと安心ですよ。
先生と話す機会は少ない!
園児の時は、送迎時に先生と話すことが出来ましたが、小学校に入学すると先生との接触がぐっと減ります。
基本、先生からの連絡は連絡帳とプリントのみです。(もちろん、怪我やトラブルがあった時は学校から電話が来たり、時には呼びされたりもしますが・・・)
入学当初は、幼稚園・保育園の時と違い、先生との接触が少ないと感じるかもしれません。でも小学校ってそんなもんなんですよね。
心配ごとがあれば小学校の先生も話を聞いてくれますよ。
トラブル等で、担任の先生の対応に不信感をもったら、学年主任など他の先生を頼るのもありです。
(わが家は1年生の時に苦労して、他の先生に相談することで解決できました!)
(スポンサーリンク)
プリントは即写真、即行動!
小学校は、先生と顔を合わせる機会がほぼないことから、基本的に学校からの連絡は「プリント」と「連絡帳」のみです。
しかもプリントも「学年だより」「学校だより」「保健だより」などいろいろあり、大切なことが複数のプリントにサラッと書いてあるんですよね。
あまりにさらっと書いてあるから、見逃したりついつい後回しにしちゃうこともあるんだけど、基本的にプリントをもらったら「すぐに写真をとって、提出物はすぐに出す」の心がけが大切ですね。
学校からの紙類は、おたよりだけでなく、テストや授業で使ったプリント、地域のイベントのチラシなど結構多いです。
小銭は必須!
小学校では、お金を子どもに持たせることがあります。
- 絵画の出品料
- ピアニカ
- さんかく定規
- 絵具
- 習字道具などなど
小学校って意外と、現金を持っていくことが多いんですよね。
提出期限ギリギリになって「小銭がない!」とならないためにも、小銭を常に常備しておくと便利です。
「すぐなくす」「すぐ壊す」と思っておく!
子どもにタイプによりますが、「子どもはすぐなくす・すぐ壊す」と思っていた方が気がラクです(笑)
でもほんとに、子どもによりけりなんですけどね。
わが家の場合は、息子はほんとすぐなくす・すぐ壊すタイプ。
反対に、娘は物を大切にするタイプで、壊れないし紛失もありません。
ちなみに、どんなものを無くしたり壊すのかというと・・・。
- 消しゴム
- 定規
- 下敷き
- 鉛筆
- 傘
- 靴下 などなど
ここらへんは、息子のようなタイプは当たり前のように無くします。しかもすぐに、何度も・・・。悲しい。
入学時に必要なものは、【2023年】小学校入学準備|購入リスト・あると便利な入学グッズ9選で説明しています。その中で無くしそうなものは多めに用意した方が無難です。
遊ぶ約束をしてくるよ!
入学してすぐにというわけでないですが、小学校に入学すると放課後や週末に遊ぶ約束をしてきます。
そこで大変なのが、家庭によってルールが違うっていうことなんですよね。
- 1年生からひとりで遊びに行くのがOK
- お友達の家はダメ、公園OK
- お友達の家はOKだけど、自分の家はNG
こんな風に家庭によって線引きがかわってきます。
どれが正解というわけでないことなので、自分の家庭なりの遊びに行くルールを決めておくと良いでしょう。
- 1年生のうちは、子どもだけで遊びにいかない
- 週末の約束は木曜日までにして、お互いの親がOKか金曜までに確認する
- 帰るときに忘れ物がないか必ず確認する
- (一人で遊びに行くようになったら)行先きは必ず教える
など、わたしの場合は最初はこんなルールで過ごしました。
また、子どもだけで遊ぶようになるとおもちゃの紛失もあります。(残念ながらわざと取られることも・・・・)



悲しいことですが、おもちゃをわざと盗るお友達もいたので、わが家はおもちゃに記名か目印をつけることに。なんてことも低学年ではありました。
「うちはうち、よそはよそ」が発動される!
「うちはうち、よそはよそ」
これ、自分が親に言われた人も多くないですか?そして、今度はそれを自分が発動することになります。
小学校にいくと、「みんなもっている」「みんなゲームし放題だ」「みんな〇〇している」など、「みんな」ってめちゃくちゃ言うようになります。
でも実際は「みんな」は2、3人だったりするわけです(笑)
(スポンサーリンク)
知り合いを作ろう!
「ママ友」は良くも悪くもありますが、やはり最低限の知り合いを作っておくと小学校生活が安心です。
小学校の連絡事項はおたよりと子どもが言うことが全てです。でも、それだとやっぱり分からないことも多いんですよね。
だからこそママ友の存在が大きいわけです。だからといって、無理に何人もママ友を作る必要はありません。
私のおすすめは、
- 自分と同じく第一子が入学している人で気が合う人
- 兄・姉がいる人で気が合う人
この二人がいるだけで、かなり楽だなと思います。
もし、そんなに簡単に知り合いは作れないという場合は、小学生のトラブルを解説してくれる「尾木ママ小学一年生 子育て、学校のお悩み、ぜーんぶ大丈夫!」という本を読むと少しは安心するかもしれませんね。
スムーズに学校生活がスタートできるために
ここまで、小学校に子どもが入学するときの親の心得をお伝えしてきました。
実際に入学で用意するものは、【2023年】小学校入学準備|購入リスト・あると便利な入学グッズ9選で詳しく紹介していますが、今回紹介したような親の心得も意外と大切です。
もちろん、すべてみんなに当てはまることではないです。でもやっぱり「入学後はこんなこともあるんだな」という知識を事前に知っておくことは大切です。入学してからしばらくは、親子ともに大変かもしれません。でも楽しいこともたくさんあります!
ぜひ今回の内容を頭の片隅において、小学校生活をスムーズにスタートできるといいなと思います。
また、新一年生におすすめの本を知りたい方は、30冊レビューしてみましたのでそちらを参考にしてみてくださいね。↓
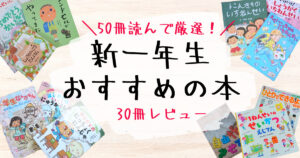
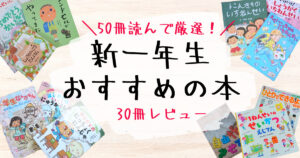
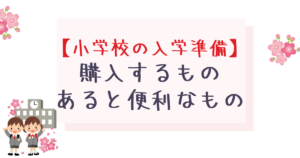
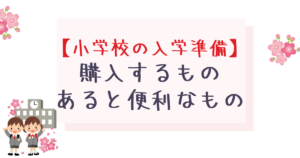


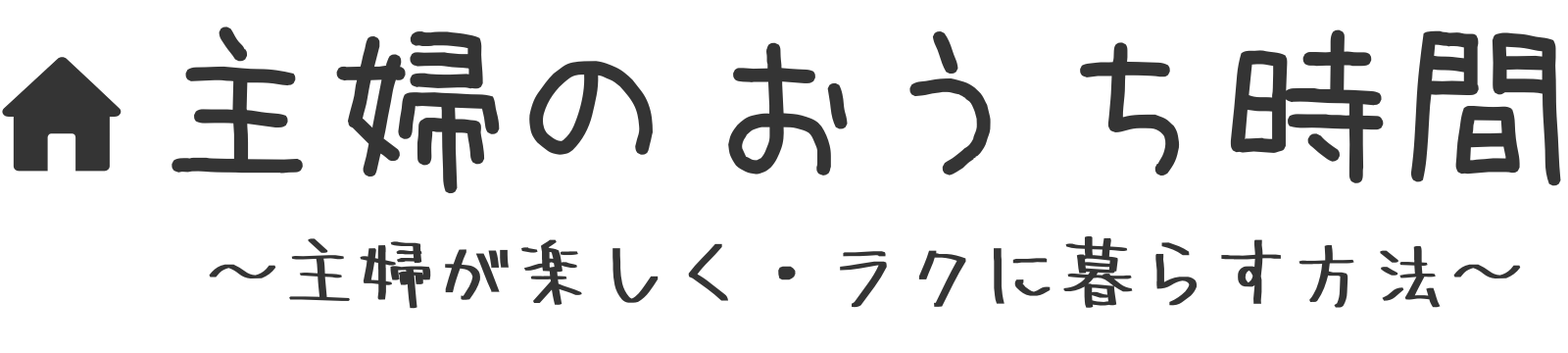
-1.png)
